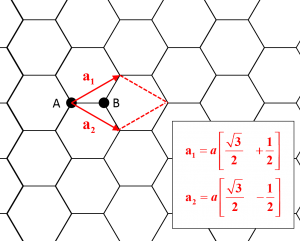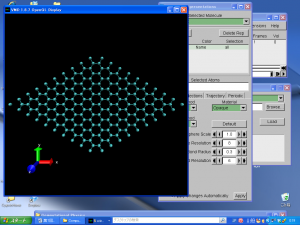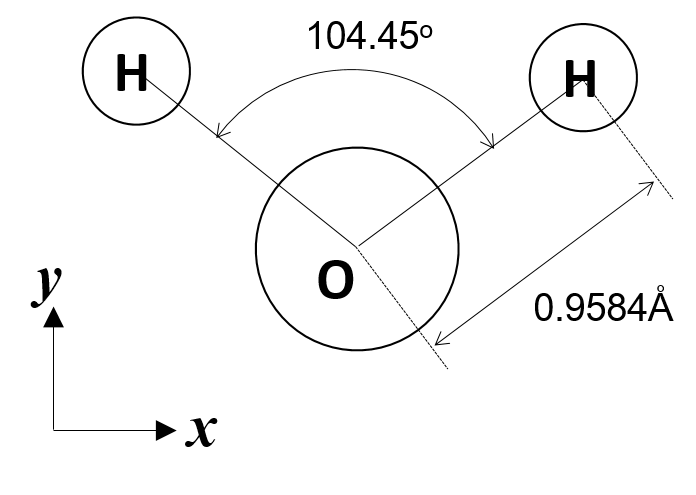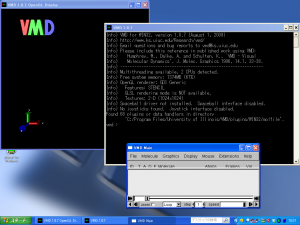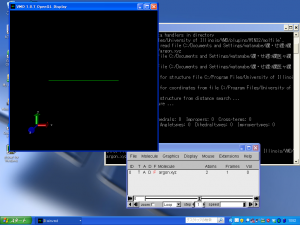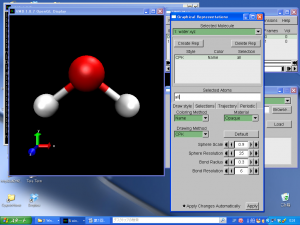Stillinger-Weberポテンシャルでは、長さの単位が\(\sigma\)=2.0951Å、エネルギーの単位が\(\varepsilon\)=50kcal/molと指定されており、含まれるポテンシャルパラメータの数値もこの単位系を前提にして決められている。しかしプログラムによっては、Å-eV単位系を使いたいときもあるだろうし、原子単位系を使いたい場合もあるだろう。
単位変換の一般的な指針
ある単位系で定義されたポテンシャル関数\(\phi(r)\)を、別の単位系のポテンシャル関数\(\phi^\prime(r^\prime)\)に変換するにはどうしたらよいだろうか? ここで\(r^\prime\)は、 \(r^\prime= \sigma r\)によって長さの単位が変えられた新しい変数を表す。元の単位系のエネルギーの単位が、新しいエネルギー単位の\(\varepsilon\)倍であるとすると、単位系の変換の前と後でポテンシャルエネルギーは同一でなければならないから
$$\phi^\prime(r^\prime) = \varepsilon \phi(r) $$
が成立するはずである。ポテンシャルの単位系を変換するには、この条件を満たすようにパラメータの数値を変換すればよい。
単位変換の具体例
次式で与えられるStillinger-Weberポテンシャルの2体項を例にとって単位の変換法を見てみよう。
$$\phi_2(r) = A (Br^{-p} – r^{-q})\exp{\left ( \frac{1}{r-a} \right )} $$
ただしここで\(r < a\)である。\(a\)はカットオフ距離と呼ばれ、2つの原子間距離\(r\)がカットオフ距離以上では、上式を用いずにポテンシャルエネルギーをゼロとする(こうしても\(r=a\)で不連続にならず、\(C^\infty\)級の連続関数になっているところがこの関数の良いところだ)。Si用のStillinger-Weberポテンシャルでは、長さの単位が\(\sigma\)=2.0951Å、エネルギーの単位が\(\varepsilon\)=50kcal/molとして各パラメータ\(A,B,p,q,a\)の値が決められている。
ここで、\(r^\prime= \sigma r\)で\(r\)を置き換えると
$$\begin{eqnarray}\phi_2(r^\prime/\sigma)& =& A (B(r^\prime/\sigma)^{-p} – (r^\prime/\sigma)^{-q})\exp{\left ( \frac{1}{(r^\prime/\sigma)-a} \right )}\\&=& A \sigma^q(B\sigma^{p-q}r^{\prime-p} – r^{\prime-q})\exp{\left ( \frac{\sigma}{r^\prime-a\sigma} \right )}\end{eqnarray}$$
となり、新しい単位系におけるポテンシャル\(\phi_2^\prime(r^\prime)\)は
$$\begin{eqnarray}\phi_2^\prime(r^\prime)& =&\varepsilon \phi_2(r)\\&=&\varepsilon A \sigma^q(B\sigma^{p-q}r^{\prime-p} – r^{\prime-q})\exp{\left ( \frac{\sigma}{r^\prime-a\sigma} \right )}\end{eqnarray}$$
となる。したがって、下の表のように新しい単位系のパラメータを定義すれば、元の関数形をほぼ維持しながら新しい単位系に移行できる。
| 単位変換前 | 単位変換後 |
| \(A\) | \(A^\prime = \varepsilon A \sigma^q\) |
| \(B\) | \(B^\prime = B\sigma^{p-q}\) |
| \(p\) | \(p^\prime = p\) |
| \(q\) | \(q^\prime = q\) |
| \(a\) | \(a^\prime = \sigma a\) |
$$\phi_2^\prime(r^\prime)= A^\prime (B^\prime r^{\prime-p^\prime} – r^{\prime-q^\prime})\exp{\left ( \frac{\sigma}{r^\prime-a^\prime} \right )}$$
指数関数の中の分子の1が\(\sigma\)に変わってしまうところが玉にキズだが、この1は長さの次元を持った量なので、本来パラメータとして扱うべきものである。